W勉強会 フォロー記事
- みうら

- 2020年8月3日
- 読了時間: 6分
7月に行いましたGLS勉強会、参加していない方のためにYoutubeにもアップしております。
DA-TE Apps! の2つの部門に対して、どうゲームを考えていくのがいいのか?という勉強会となります。
簡単にいえば、フリー部門は「面白いゲーム」を作るにはどうすればいいか?
GLS for Educaion部門は「売れるゲーム」を作るにはどうすればいいか?という観点になります。
2つの部門の違いはゲームコートのブログの方に書いたので、そちらをご覧ください。
今回は、こんな長い動画見てらんないよーって人のための超ざっくりとした要約記事になります。
気になったら動画も見てね!
フリー部門企画勉強会
フリー部門の勉強会のテーマは「イケてるゲームのコンセプトメイク」
日本ゲーム大賞 アマチュア部門、福岡ゲームコンテスト(GFF AWARD)の大賞作品を例に「イケてるゲーム」とは何か?「イケてないゲームとは何か?」を考えました。


当たり前じゃん!って感じでしょ?
その当たり前が難しいんですよね……。
学生が初めて作ると大体イケてないゲームになります。
ゲーム大好きで、ゲーム開発者になろうと専門学校に入り、まあまあ自由にゲームを作れる環境にいるにも関わらず。
それはなぜか?

そもそも「ゲームとは何か」が分からないからじゃないかと思うんですよね。
ゲームってなんでしょうね?
考えた人は先に進んでください。

出典
クロフォードのゲームデザイン論(クリス・クロフォード)
コスティキャンのゲーム論(グレッグ・コスティキャン / 資料内の文章はルールズ・オブ・プレイより引用)
ルールズ・オブ・プレイ(ケイティ・サレン, エリック・ジマーマン)
ゲームデザインバイブル(ジェシー・シェル)
いろいろな人が言ってきた内容の大きな共通点は


僕はゲームをこの形で考えています。
もちろん違う意見の人も多いので、いろいろ調べてみてください。
重要なのは、ゲームを作るうえで何を達成したいかを明確化できるものです。
イケてないゲームは、必要な目標と、満たしたい感情が抜け落ちているか、わかりにくいからそうなるんじゃないかなと。
じゃあ目標と感情を考えれば大丈夫?
いえいえあと2つ考える必要があります。

企画の学生は企画の授業でやるんじゃないでしょうか。
そして、聞いてもようわからんとなったのじゃないでしょうか(学生時代のみうら)
コンテストの場合この2つは決まっています。


ターゲットと環境に対する、他の具体例は動画を見てください。

「ターゲットに対して刺さるゲーム」と「遊ぶ環境」を想定して「目標と感情」を考える必要があります。
たとえば就活の時、採用担当者は忙しい中ゲームを遊びます。そして、多くの応募者の中で目立つ必要があります。
コンテストと同じターゲットと環境が適用できますね。
そうなると長大なゲームを送るのは戦略として好ましくない、となります。
イケてるゲームは、それらすべてがマッチして、「目標と感情」のど真ん中を射抜けるゲームなのです。


表にまとめると、イケてるゲーム、イケてないゲームがどんなものかなんとなく見えてきたんじゃないでしょうか。
あとは開発時に、ここを外さなければ大丈夫です。
感情をベースにしたコンセプトメイクの方法として、まず与えたい感情から逆算しましょう。

自分がゲームを遊んでいる時、どういう感情を抱いているかも考えてみましょう。
ただのゲーム好きと、開発者を分けるのはゲームを遊んでいるとき、どういう感情をあたえる仕様なのかを考えがちな所かもしれません(職業病)


そして、与えたい感情になるにはどんなシチュエーションか、ターゲットや環境にマッチしたシチュエーションはどんなものかを深堀りします。

すごく楽しそうですね(自賛)

出てきたゲームのアイディア、与えたい感情、達成したい目標、そんないろいろを一言にまとめます。

企画の授業でやりますよね。そしてようわからんとなりますよね?(学生時代のみうら)
コンセプトは「このゲームを遊んだ人間は、絶対こうなる」と書いたものです。
ゲームを遊んだの部分は、作るプロダクトに応じて変えてもいいです。

そしてコンセプトメイクの仕方、そこからの開発の考え方を中心に説明しています。
まとめるとフリー部門で求められるゲームは
ターゲット(審査員)の感情をゆさぶる、遊ぶ環境(コンテスト会場での試遊)にあったもの
フォーカスすべきは、感情をゆさぶれるか否か、他より目立つかどうか
ボリュームは不要、むしろ審査員が遊ぶ5分が最高ならそれでいい
となります。
GLS for Education部門企画勉強会

一方のゲーム開発塾こと GLS for Education部門、今年もKPIで勝敗を決めます。(KPIについては去年の記事を見てください)
ハイパーカジュアルとよばれる、ものすごくシンプルな広告型のゲームで勝敗を決めます。


こちらは実際に市場に配信するので、重要になるのは数値です。
お客様一人から得られる売上(LTV)と、お客様一人を獲得するのに必要なコスト(CPI)からROASという値を計算して、将来性を算出し、一番高いチームが優勝となります。

計算式が入るのでうえ~となりがちですが、言ってることは実に単純。



ゲームとは何か?感情を揺さぶれるか?とか、そういう深い議論はこっちではあまり重要視されません(もちろんしたほうがいいですが、それだけでは勝てません)
ハイパーカジュアルゲームを遊ぶお客様は、ゲームというより、もっと手軽で気持ちいい
暇つぶしを求めている傾向が高いです。
また、実際に広告を配信して海外の多くのお客様に遊んでいただくため、パッと見でわかるテーマも重要になります。
キャラクター性や世界観が、かえって脚を引っ張ることもあったりもします。
面白いゲームが売れるゲームとは限らず、売れるゲームが面白いとは限らないのです。

まとめるとGLS for Education部門で求められるゲームは
何より分かりやすく、パッと触って遊べるゲーム
フォーカスすべきは、分かりやすいことと、次の日も触りたいと思えること
ボリュームはある程度必要、実際にリリースするためバグもある程度落とす必要がある
となります。
ルールの違い=目標の違い
比べてみると結構考え方が違うのが分かりますね。
フリー部門
ターゲット(審査員)の感情をゆさぶる、遊ぶ環境(コンテスト会場での試遊)にあったゲーム
フォーカスすべきは、新しく、分かりやすく、高品質で、そして他より目立つかどうか
ボリュームは不要、むしろ審査員が遊ぶ5分が最高ならそれでいい
GLS for Education部門
何より分かりやすく、パッと触って遊べるゲーム
フォーカスすべきは、何より分かりやすいこと、次の日も触りたいと思えること
ボリュームはある程度必要、実際にリリースするためバグもある程度落とす必要がある
作品としてのゲーム作りと、商品としてのゲーム作りの差と見ることもできます。
審査形態に応じてゲームの中身も変わってくる、というお話でした。
この記事だとざっくりしすぎて、分かりにくい部分も多いと思うので……
気になったら動画も見てね!!!!!!


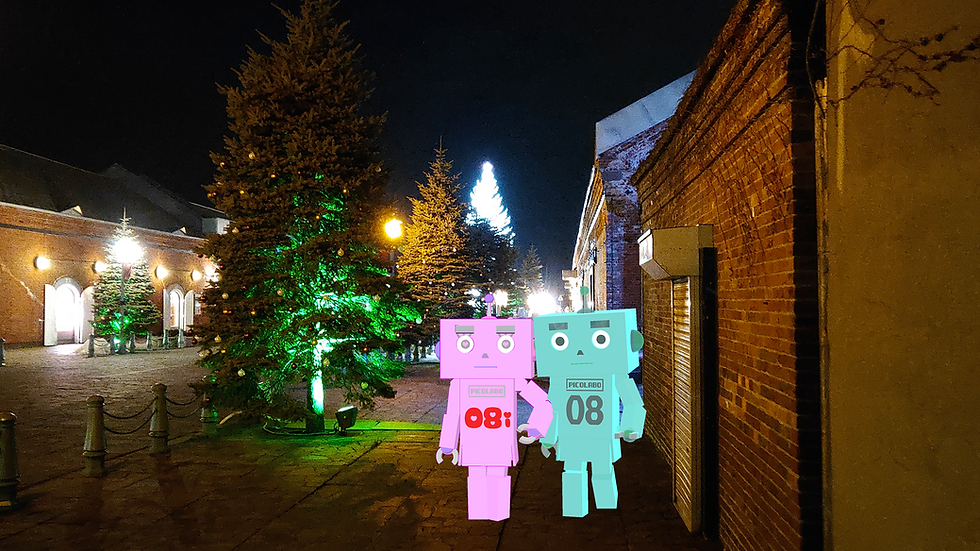

コメント